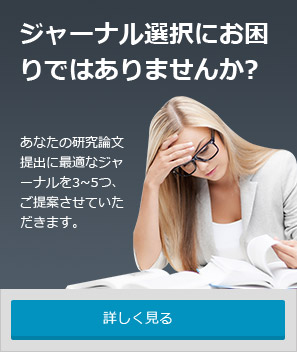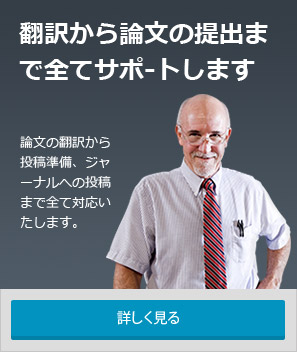論文執筆は、どこまでやれば「十分」か?
オーストラリア国立大学(ANU)のインガー・ミューバーン教授のコラム「研究室の荒波にもまれて(THE THESIS WHISPERER)」。今回は、研究や論文執筆において、どこまでやれば「十分」なのか、という悩ましい問題について解説します。
私はもう10年以上、博士課程の学生だけを相手に仕事をしてきました。マルコム・グラッドウェル(Malcolm Gladwell)が言う「専門家になるために必要な10,000時間」を積み重ねたので、自分は研究教育問題の専門家であると言わせてもらいます。
「専門家」という称号を本当に名乗れるようになるしるしのひとつは、自分が遭遇した問題を認識し、即座にテーマに分類するようになることです。これは、純粋な専門知識とは異なる「実践における知識」の一種です。博士課程の学生が抱える問題で最も一般的なものは、「指導教官が悪い」、「研究デザインが悪い」、「残された時間が少ない」です。私が長年見てきた「こんなの書けない!」という問題のバリエーションについてはここでは触れないでおきます(実際、この問題についてはショーン・レーマン(Shaun Lehmann)とキャサリン・ファース(Katherine Firth)と共同で一冊の本を書きました)。
ここ数年、研究教育の実践の中で、本当の意味で新しい問題に遭遇したことはありません。専門家である私には、どんな状況にも適用できる対応策や行動の「レパートリー」があります。博士課程の問題のほとんどには、励ましの言葉、ホワイトボードの図、本、新しい戦略の提案などといった解決策がありますが、中には解決策のないものもあります。最も困難で手に負えない博士課程の問題は、「どこまでやれば、十分やったといえるのか?」というものです。
この問いは、文献、データ収集、単語数、アイデア出し、参考文献など、あらゆる場面で質問されます。どれくらいの量であれば十分なのか?学生も論文も、それぞれ異なるため、「十分さ」という問いに対する明確な答えはありません。状況によって大きく左右されるこのような問題に対し、私は断片的な答えしか提示できませんが、ここではそのうちの3つと、それぞれに対する戦略を紹介します。
文献を十分に読んだと判断するには
この問いに対する唯一の答えは、「一生わからない」です。毎年発表される論文の数をキリマンジャロ山に例えた人がいますが、これは頂上に降り積もる雪の層を、2回以上ダウンロードした論文になぞらえたものです。学術の産物がおそろしく過剰に生み出されているのです。あらゆるテーマの文献が山ほどあるため、高山病を避けるには、明確な基準で引いた境界線を設定するようにしなければなりません。
1つの方法として、自分のテーマに関連するものとそうでないものの判断基準を挙げておくことをおすすめします。例えば、研究の進展が速い分野では、3年前まで、5年前までなど、時間を基準にして関連性がありそうなものだけを読み返すようにします。あるいは、地理的な場所、時代、参加者のタイプなどで絞ったトピックの中に読む指針となる強いテーマがあるかもしれません。例えば、小学生に関する論文を書くのであれば、高等教育に関する文献を読む意味はほとんどないでしょう。また、「研究方法」も基準を決定するための強力な指針となり得ます。科学的な研究をするのであれば、質的研究を参照することに意味はないかもしれませんし、その逆もしかりです。もちろん、例外はありますが、研究方法を混ぜ合わせることには慎重になるべきでしょう。
何をするにしても、論文中のどこか、できれば文献レビューのセクションで、設定した基準について説明する必要があります。政治的、理論的な理由から、非常に具体的な基準を独自に設定する人もいます。引用するのを先住民の研究者に限定した学生や、女性の著者のみを引用した学生にも出会ったことがあります。このような戦略にはリスクが伴いますが、私は、十分に検討された理由があれば、うまくいくはずだと思います。
実践:自分の選択について振り返り指導教官と話し合うため、文献検索に用いた戦略と基準について1~2段落の短い文章を書いてみましょう。
十分な独自性があるかを、どう判断すればよいか
オリジナリティの問題は悩ましいものです。多くの人は、オリジナリティが足りないこと、あるいは反対に独自性を追求し続けて研究を続ける間に誰かに先を越されることを心配します。自分の研究を他の研究者が盗み、先に発表される「スクープ」の問題もよく起きることで、より一般的に取り挙げられる問題でしょう。独自性の問題を解決するために、多くの研究者が学際的な研究を進めることでオリジナリティを実現していますが、意図しない副作用が生じることもあります。私は、独創的すぎるという問題を抱えた学生を少なくとも1人指導しました。その学生は、音楽学とファジー理論を融合させていたのです。面白い組み合わせでしたが、彼女の学位論文の執筆には大きな困難が伴い、特に審査官を選ぶのが大変でした。
学際的な論文を書く場合、その論文の主な読者が誰であるかをしっかり考えておくことが極めて重要です。私の卒論は、建築の授業におけるハンドジェスチャーについてでしたが、教育者を想定読者とすることを意識しました。それにより、方向性を失うことなく人類学や社会学から必要なものを取り入れられました。建築を学ぶ学生の間でもジェスチャーを研究している人はたくさんいましたから、人類学だけでは、この論文に独自性はなかったでしょう。しかし、建築の教育理論や実践との関連でジェスチャーを研究していた人はいなかったので、私は自分のニッチを見つけることができたのです。
実践:論文の読者について、1段落程度の文章を書いてみましょう。どのような人たちなのか?自分のテーマについて何に興味を持ったのか?自分の論文だけが、彼らの知識に資するのはどのような点か?
十分に書けたか
この問いに対する口当たりの良い(そしてほぼ正しい)答えは、「大学が指定した文字数に達した時点で十分(!)」です。しかし、真面目な話、多くの審査官が短い論文を好むことも明らかになっており、適切な長さとは何かというのは「Wicked Problem (問題や何をして解決するかを定義することさえ困難な、厄介な問題)」といえるかもしれません。個人的には、上にリンクした文献に基づき、単語数は8万ワードまでに留めるように学生たちに勧めています。とはいえ、これは厳密なルールではなく、経験則のようなものです。最近、ある同僚と議論したのですが、彼は私たちの大学に提出される論文があまりにも「薄っぺらい」ことを懸念していました。彼の懸念は、学会やセミナーでの先輩たちとの議論に基づくものです。そして、「最近の若者は!」との思いが強いのは、論文を短くする傾向への反動かもしれない、という結論に私たちふたりは至りました。理由はどうあれ、どのようなものにも流行や規範はあります。それぞれが自分の専門分野での流行や規範を探り出し、それに対して自分がどう対応するかを考えることなのです。
実践:できるだけ多くの年長者に、論文の長さはどれくらいが適切か聞いてみましょう。もし答えられない場合は、最も一般的な長さを聞いてみます。長いものが好きか、そうでないのか、彼らの反応を測ってみます。回答はしっかりメモしておきましょう。すべての数字を合計して平均値を出すか、どの数字が最も肯定的な反応を引き出したかに基づいて論文の長さを決めましょう。
「十分さ」に関する問題解決において、この投稿が多少なりともお役に立てれば幸いです。この種の問題に関して私が自信をもって言える唯一のことは、自信満々に答えを出す人は要注意だということです。専門家であれば、慎重になるべきタイミングがわかるものですが、この種の問題に対して断定的になるのは、その人が研究教育アドバイザーとしては素人であることの証なのです。
ストレートな答えが得られないような問題はありますか?ブログのネタになりそうなので、ぜひお聞かせください!