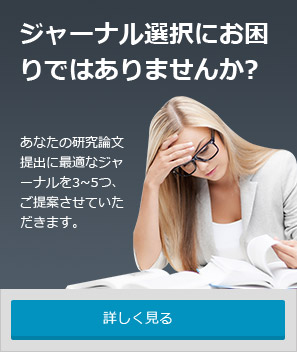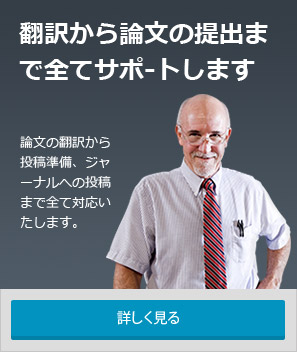博士課程のニューロダイバーシティ(発達障害)
(訳者注:本記事のテーマである「ニューロダイバーシティ」は日本語では一般的に「発達障害」と呼ばれる脳機能の特性を表す語ですが、筆者の「障がい」ではなく「特性」であるという考えを尊重し、以降、「ニューロダイバーシティ」と表記しています。一目で内容を分かりやすくするためタイトルに「発達障害」という表現を使用していますが、何卒ご容赦ください。)
_________________________________________________________________________________
まさか自分が泣くとは思いませんでした。
私は感情的なテーマを研究することはあまりありません。「トラブル・トーク(troubles talk)」や管理システム、博士号取得後の雇用可能性などを研究してきましたが、ニューロダイバーシティ(脳の特性による個性の多様性)と博士号取得後の経験に関する今回の研究はそれまでの研究とは違います。学術的な文章に感動して涙したのは、間違いなくこれが初めてです。それは、この研究が個人的なものだと感じられたからでしょう。
どこかの博物館に「普通の脳」として解説される「瓶に漬けた脳」など存在しないとトニー・アームストロング(Tony Armstrong)は言うものの、私自身は自分を「定型脳」かなと思っています。でも、ニューロダイバーシティについて読めば読むほど、自分自身に対する疑問が湧いてきます。私には、過集中状態に陥る能力などADHDの特徴もあれば、連想思考やルーティーンを強く求める性向など自閉症的な特徴もあります。しかし、私はどちらのタイプのニューロタイバーシティの診断基準にも当てはまらないし、自分の「癖」を障害とは感じていません。例えば、社会的な状況での曖昧さに比較的慣れているし、「やるべきこと」リストの優先順位付けに苦労したり、「タイム・ブラインドネス」(時間の感覚があいまいで上手く時間を把握できないこと)を経験したりすることもありません。
しかし、血縁も、結婚相手の家系も含めた、私の家族の多くはニューロタイバーシティの特性を持つことが分かっています。家族が正式な診断を受けるようになったのは、子どもたちが学校に入って以降、ここ15年ほどのことです。子どもたちはそれぞれ、いろいろな意味で学校に行くことに辛さを感じていました。教師たちの名誉のために言っておきますが、彼らは子どもたちをただあがき苦しませていたわけではありません。70年代や80年代から、教育は劇的に進歩していたのです。ニューロタイバーシティが認識され、子どもたちは勉強するためのスキルや意見を言うためのスキルを教えられています。対照的に、私を含む家族の中の大人のほとんどは、学校では勉強面でも人付き合いでも苦労してきました。それでも自分たちが変人や、オタク、個性派である、などと思って納得してきました
現在では、こうした個性に名前が付けられています。自閉症、ADHD、強迫性障害、ディスレクシア、トゥレット症候群などです。
私は日々、ニューロタイバーシティ特性を持つ家族の驚くべき長所と才能を目の当たりにしています。学校生活や人生におけるさまざまな葛藤の中で、私は彼らとともに歩んできました。成功を祝い、助けられるところは助けてきました。でも、時には助けや共感が足りないこともありました。定型発達寄りの私は、ニューロタイバーシティ特性を持つ家族の行動を不思議に思ったり、迷惑に思ったり、苛立たしく思ったりすることがあるのです。逆に、私の定型発達的な期待や要求は、彼らにとって迷惑で、いらいらさせる、理不尽なものなのです。
イライラしたり、腹が立ったりしたときは、自分自身に言い聞かせるようにしています。自分たちは発見の旅の途上にいるのだと。私たちは皆、お互いに愛と優しさと忍耐の蓄えを見つける必要があるのです。そしてたいていの場合、私たちは上手くやっていると思います。
ここ10年ほどの間に、私自身のニューロタイバーシティへの認識が深まるにつれ、博士課程の学生を含め、いかに多くの研究者が私の家族と似ているかということに気づかずにはいられなくなりました。それが、私が学問の世界を快適な業界だと感じる理由のひとつだと思いいます(人々が文字通り「家族のように馴染み深い=familiar」なのです)。
学問の世界では、自閉症の特徴である「特殊な興味」と過集中の傾向がある人が多く、また、ADHDに特徴的な、好奇心や創造性を常にうずかせている人もいます。才能と苦労は隣り合わせなのです。自閉症スペクトラムの人は、学生よりもスタッフのように振る舞うことが求められる(学部内の人間関係や政治に関わることも含めて)、博士号取得レベルの学問の場の非常に社交的な性質に戸惑うことがあります。ADHDの人は、好奇心によって開かれた多くのウサギの穴に落ちていくうちに、博士号の射程が広がりすぎて制御不能になっていることに気づくかもしれません。
非定型発達の脳が、長時間の読書や分析に必要な集中力の発揮に困難をきたす場合がありますが、理由は様々です。光や音に対する感覚に問題がある人もいれば、単にじっとしているのが苦手な人もいるのです。
もちろん、2つとして同じ脳はなく、私の甥の1人のように、自閉症であると同時にADHDであることもあります。また、この甥のように、適切な条件下で素晴らしい才能を開花させることもあります。しかし、私の家族の他の人々のように、平均的な才能の場合もあります(ニューロダイバーシティ特性の人々に他の領域の「才能」を期待するのはある種の障がい者差別です)。また、私のように、ニューロダイバーシティの特徴をいくつか持っていても、特定の疾患の診断基準を満たさない人もいます。同じ脳は二つとないのです。だから、ニューロダイバーシティの経験は膨大で多様で、ジェンダーや階級、民族といった他のアイデンティティとも交錯します。
つまり、複雑なのです。
私は(おそらく証明不可能な)仮説を立てていますが、大学には、おそらくIT業界を除けば、他のどの職業よりもニューロダイバーシティ特性を持つ人が多いでしょう。しかし同時に、ニューロダイバーシティは、学問やアカデミズムに関する議論において、そのほとんどが隠され、目に見えず、否定され、無視されています。現役の研究者におけるニューロダイバーシティに関する研究はほとんどありません。存在する研究では、例えば、学問の場における自閉症のスペースの創出に関するこの論文のように、学問の「規範」に根本的な疑問を投げかけています。しかし、私はそのような研究を行っている学者に賛辞を惜しみませんが、一方で多くの個人が自分のニューロダイバーシティ特性を公表することに恐れや不安、疑念を感じているのではないかと思います。
生活していくために、ニューロダイバーシティ特性のある人々はしばしば「仮面」をかぶらなければなりません。仮面をかぶるには、ソーシャルインタラクション(社会的相互作用)のたびに、自己と他者を監視し続ける必要があり、これは正直言って疲れます。仮面をかぶることは、ただでさえ忙しく、競争の激しい学問的環境において何らかの役割を果たす上で、余計な負担を増やすことになりますが、人々は自分のニューロダイバーシティ特性を公表するのが怖くて、仮面をかぶるのです。『障害者』というレッテルを貼られたくないのです。特に、自分のニューロダイバーシティ特性をひとつの「状態」ではなく、「治す」必要のある自分の一部として経験している人ならなおさらです。
スティグマは実際に存在します。
私がポッドキャストやソーシャルメディア、そしてこのブログでニューロダイバーシティについて話し始めて以来、多くの人が自身のニューロダイバーシティ特性を私に明かしてくれました。そして、大学の経営幹部、ハイレベルの管理職、有名な学者、そして講師、ポスドク、博士課程の学生など、学術界のあらゆる分野にニューロダイバーシティ特性のある人々がいるのです。ニューロダイバーシティ特性を持つからといって、学問の世界で成功できなくなるわけではありませんが、日々の学問的生活がより困難になることもあり得ます。
ニューロダイバーシティ特性のある研究者は、以前は「高機能」と呼ばれていました。診断を求めたことがない人も多いのは、具体的な障壁に直面するまで「障害」を感じないからです。ヘレン・カーラとエイミー・グラントが主張するように、そうした研究者はニューロダイバーシティ特性を学業上の利点として経験していることさえあります。「高機能」という言葉は、障害の原因は本人ではなく世界にあることが多いという認識が広まることによって、あまり使われなくなりました。世界がユーロダイバーシティ特性のある人々が成功できるような構造になっていれば、そうした人々は成功できるし、成功するのです。しかし、その構造がうまく構築されていなかったり、突然変わってしまったりすると、ニューロダイバーシティ特性の人々は苦労することになります。
例えば、ADHDの人は、博士課程に進むまでの定められた課題は十分に上手くやっていけても、博士号取得の段階で苦労することがあります。好奇心の赴くままに行動するのが好きで、時には時間通りに場所に行くのに苦労することもある人々にとって、時間的にも課題的にも柔軟な博士課程の仕組みは、定められた課題をこなすのと比べて魅力的なものに違いありません。しかしおそらく、制限的で苦痛に思える定められた課題を行う研究の構造が、実はニューロダイバーシティ特性を持つ脳の成功を、陰ながら支えてていたのでしょう。
短期の激しい努力が報われる課題型研究の「エピソード」的な性質は、ゲーマーが「研磨」と呼ぶような多くの作業を伴う博士号のスローワークよりも、ADHDに優しいかもしれません。同様に、課題型研究において学習への道筋や達成基準が明確にマッピングされていることは、自閉症スペクトラムの人々が不安やストレスに対処する助けとなります。ニューロダイバーシティ特性を持つ人々はしばしば明確な指導や指示を必要とし、またそれを望んでいますが、多くの指導教官は、それが学問的自立や創造性の発達を妨げるという誤った思い込みのもと、そうした指導や指示を提供することに消極的なのです。
まさに、定型発達といった思考です。
私には(まったく証明不可能な)第2の仮説もあります。アカデミアはもともと、ニューロダイバーシティ特性のある人々を受け入れるために構築されたのに、時代とともに受け入れられなくなってきたという仮説です。
オックスブリッジ(オックスフォードとケンブリッジの併称)の伝統を受け継ぐ修道院スタイルの大学のカレッジについて考えてみましょう。これを書いている今、私はケンブリッジのウルフソン・カレッジの中にいて、日当たりの良い庭を眺めながら快適なデスクに座っています。人里離れた静かで孤独な場所ですが、そうである必要はりません。オックスブリッジで言うところのカレッジとは、アカデミックな生活のあらゆる面をサポートするために設置された、巨大なアカデミック・シェアハウスのようなものです。望めばここで眠ることもできますし、私の魅力的なオフィスから数歩歩けば食堂があり、そこで食事をし、一緒に過ごすオタク仲間を見つけることもできます。
ここでは、大学の規則が儀式化されているため、私はいつもつまづいてしまいます。どの夕食が正式で、どの夕食がそうでないか、いつ食べるか、食器はどこに置くか、食堂とクラブハウスや談話室ではどんな交流が許されるか、などです。ケンブリッジの文字通りの門番である大学のポーターは、質問に答えたり、鍵をくれたり、落し物を見つけてくれたり、芝生の上を歩くなと言ってくれたりするだけでなく、おそらくどんなロジスティクスの問題も解決してくれるでしょう。
そして、ケンブリッジやオックスフォードのような大学内の学術コミュニティの一員であることは、かつては(そしてある意味では今も)、一生ついて回ることでした。私は、生涯を大学で過ごした「バチェラー・フェロー」と呼ばれる学者たちの世話をしている、ある大学の上級学者に話を聞きました。このような高齢の学者たちは、老人ホームに移されるのではなく、大学内で「介助付き生活」という形でケアされていました。また、地域社会とのつながりを維持するために、大学の食堂に顔を出す高齢の学者たちにも出会いました。とても人道的で、まさに私が望んでいるような老後の世話のされ方です。
そして、ケンブリッジやオックスフォードのような大学内の学術コミュニティの一員であることは、かつては(そしてある意味では今も)、一生ついて回ることでした。私は、生涯を大学で過ごした「バチェラー・フェロー」と呼ばれる学者たちの世話をしている、ある大学の上級学者に話を聞きました。このような高齢の学者たちは、老人ホームに移されるのではなく、大学内で「介助付き生活」という形でケアされていました。また、地域社会とのつながりを維持するために、大学の食堂に顔を出す高齢の学者たちにも出会いました。とても人道的で、まさに私が望んでいるような老後の世話のされ方です。
これらの大学は、知に生涯を捧げる(白人の)男性たちが集まるように設計されていました。彼らが教えていたのは、蛍光灯に照らされた部屋で30人や40人での騒がしい授業よりも感覚的な問題が少ない、少人数制か1対1の授業でした。長い間、彼らは独身であることが求められていましたが、人間関係を苦手とする人々にとっては、おそらく問題はなかったのでしょう。アイザック・ニュートンは社交的でなかったことで有名で、少なくとも、ある伝記作家は彼を自閉症と診断しています。大学での隠遁生活は、明らかにニュートンに合っていたのです。少なくとも、彼が生み出した成果という点では、その結果に異論の余地はないでしょう。
オックスブリッジは、自分の面倒を見ることができない、あるいは見ようとしない人々の面倒を見る、思考のための装置なのです。特権的な場でしょうか?そうです。排他的でしょうか?まさにそうです。ニューロダイバーシティに優しい場でしょうか?そうかもしれません。
私たちの多くが居を定める、企業化され、新自由主義に走り、資金繰りに行き詰まった大学は、もはや考えるための装置としての大学ではありません。私たちは今、自分たちで洗濯をし、多くの書類に記入し、社会生活を管理し、大勢の学生を教え、お金や資源や地位を奪い合います。私たち定型発達の人間の多くも、現代のアカデミックな生活に苦労していますが、私たちの中のニューロダイバーシティ特性の人間にとっては、その苦労はさらに大きくなります。
学問の世界を再びニューロダイバーシティ・フレンドリーにし、その過程で私たち全員にとってより良いものにするためには、努力が必要です。オックスブリッジのモデルは、おそらく進むべき道ではりません。特に、ニューロダイバーシティ特性の人々がより安心して「カミングアウト」し、成功するために必要なことを伝えられるような場を作る必要があるでしょう。
話は始まりました。涙が出るほど感動したのは、ジム・シンクレアによる『Don’t mourn for us(私たちのために嘆かないで)』という講演の中の一節です。これは自閉症児を受け入れる両親についての話ですが、メッセージはそれだけにとどまらず普遍的です。
「私たちにはあなたが必要です。私たちにはあなたの助けと理解が必要です。あなたの世界は、私たちに対してあまり開かれていません。あなたの強いサポートがなければ、私たちはやっていけません。そう、自閉症には悲劇がついて回ります。私たちが何者であるかが原因ではなく、私たちに起こることが原因で悲劇は起こります。もし悲しみたいのなら、そのことについて悲しんでください。でもただ悲しむよりも、そのことに腹を立て、そのことに対して行動してください。」
連帯して
インガー
追記:多くの人がこの研究に興味を示してくれたので、博士課程におけるニューロダイバーシティ・メーリングリストを立ち上げました。今後の展開に興味がある方、あるいはこの先の研究に関わる可能性のある方は、こちらから登録できます。