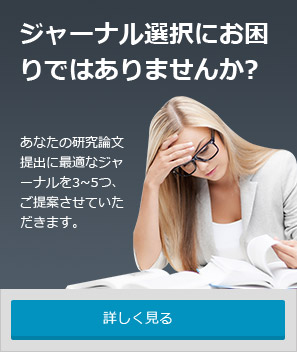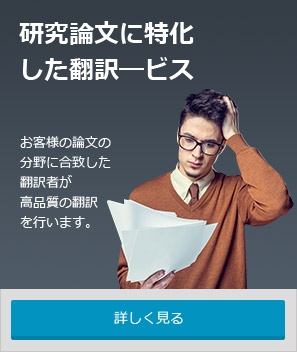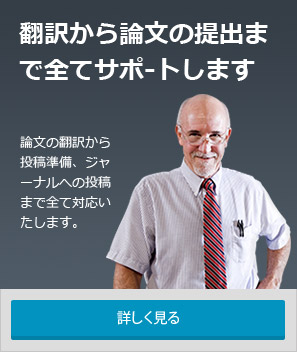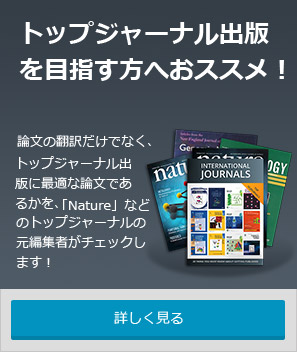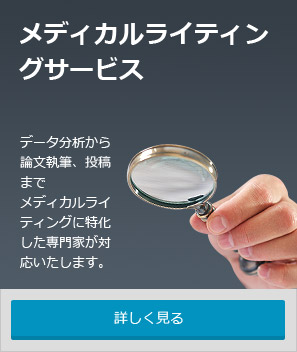助成金の申請書は「技術文書」ではなく、「セールス文書」のつもりで!
どんな研究を行うにせよ、そのためには予算が必要です。昨今ではどの分野でも、所属する研究機関に頼ることなく、自分で研究費を獲得することが求められています。いや、研究費を獲得する能力もまた、研究者としての能力の一部だという認識も広がっています。読者のなかにも、各種助成金を求めて申請書を書いたことがある人もいるでしょう。英語エディターのウィリアム・スティーブンソンとリサーチクライマーズ通信編集部が申請書を書くさいのヒントを提案します。
* * *…