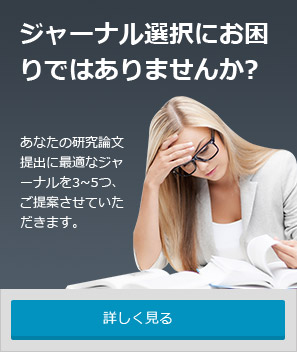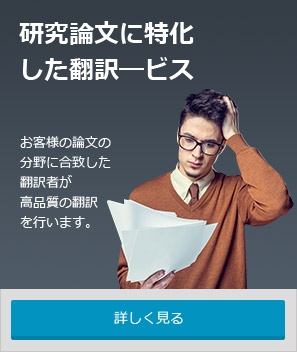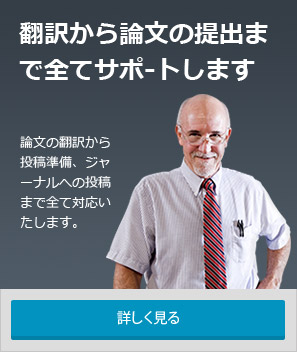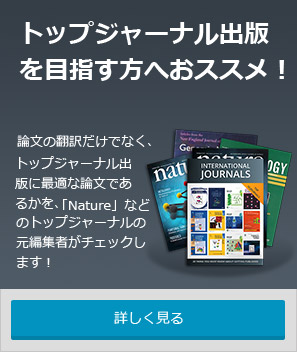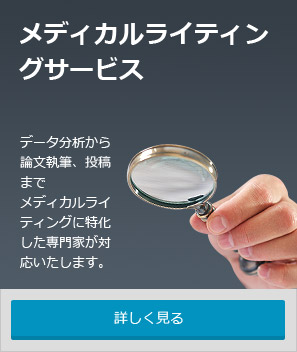論文執筆者に識別IDは必須?新しい識別システム「ORCID」
「名前がなんだっていうの?」。シェークスピアのジュリエットは「そんなの、なんでもないわ」と言いましたが、研究者にとって名前は重要です。私たちは自分の研究について承認されたいと思います。また、ほかの誰かに承認を譲りたくないし、自分たちのものではない研究成果を横取りしたくもありません。このことは、今日の出版状況においてはリアルな問題になっています。もしあなたが「ウィリアム・スティーブンソン(William…
デジタル実験ノートはあなたにピッタリ?
「STAP細胞」をめぐる研究不正事件で問題になったことの1つに「実験ノート」の問題があります。小保方晴子・理化学研究所ユニットリーダーは、実験結果を記録する 実験ノート…
「この人には査読されたくない」と指定してもいいですか?
「尊敬できない」、「以前、侮辱されたことがある」、「この分野に関しての考え方が根本的に違う」……。どんな正当な理由があるにしろ、この狭い学界という世界で 「この人にだけは査読されたくない」という人間関係はつくりたくないものです。しかし、実際にそういう人がいたとしたら、どうしたらよいのでしょうか? 万が一にも自分の論文がその人へ廻されたら、絶対に公平な評価はしてもらえない……。そんなときには、編集部に理由を話して、少し考慮してもらえないかお願いした方がよいのでしょうか?…
投稿論文の査読中に新しいデータが出てきたら?
ジャーナルによる査読期間は、ときには1年近くに及ぶこともあります。そのため、論文の草稿をジャーナルに投稿した後も関係のある研究を引き続き行っていると、最初の論文の査読中に新しいデータが積み重なる可能性も出てきます。このような場合、どうしたらいいでしょうか?…
査読者になることのススメ
一般的にいって、誰が学術雑誌の査読者になるかと問えば、「その研究分野において国際的に認められた研究者であるとともに、論文の出版数が多いなど生産性、 客観的な観察力、論点を明確に示すことのできる語学力のある人」という答えが返ってきます。しかし現実には、限られた人員で構成された編集委員会が、…
査読者は「違いの出た研究」に好意的になりがち?
「AとBはまったく違いがない」という研究結果は、「AのほうがBより効果(影響)がある」という研究結果と同様に重要な発見のはずです。ではどうして、学術雑誌は「AのほうがBより効果(影響)がある!」という論文のみであふれているのでしょうか?…
論文を投稿するジャーナルの選び方
どんなに一生懸命研究し続けても、その結果が論文として学術誌に掲載されなければ意味はありません。そうかといって、ただやみくもに『ネイチャー』や『サイエンス』のようなトップジャーナルに投稿し続けても、徒労に終わるだけですよね。自分の分野や目的に適したジャーナルを選ぶ必要があるのです。エナゴ英語エディターのウィリアム・スティーブンソンの協力のもと、ジャーナル選びのコツを紹介します。
* * *…
X
今すぐメールニュースに登録して無制限のアクセスを
ユレイタス学術英語アカデミーのコンテンツに無制限でアクセスできます。
* ご入力いただくメールアドレスは個人情報保護方針に則り厳重に取り扱い、お客様の同意がない限り第三者に開示いたしません。